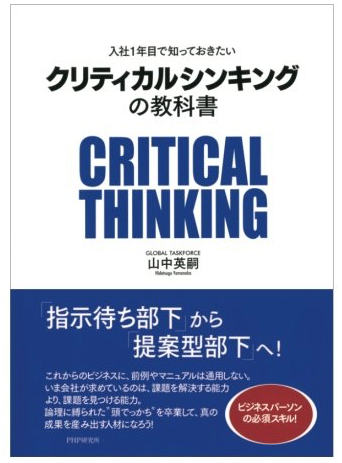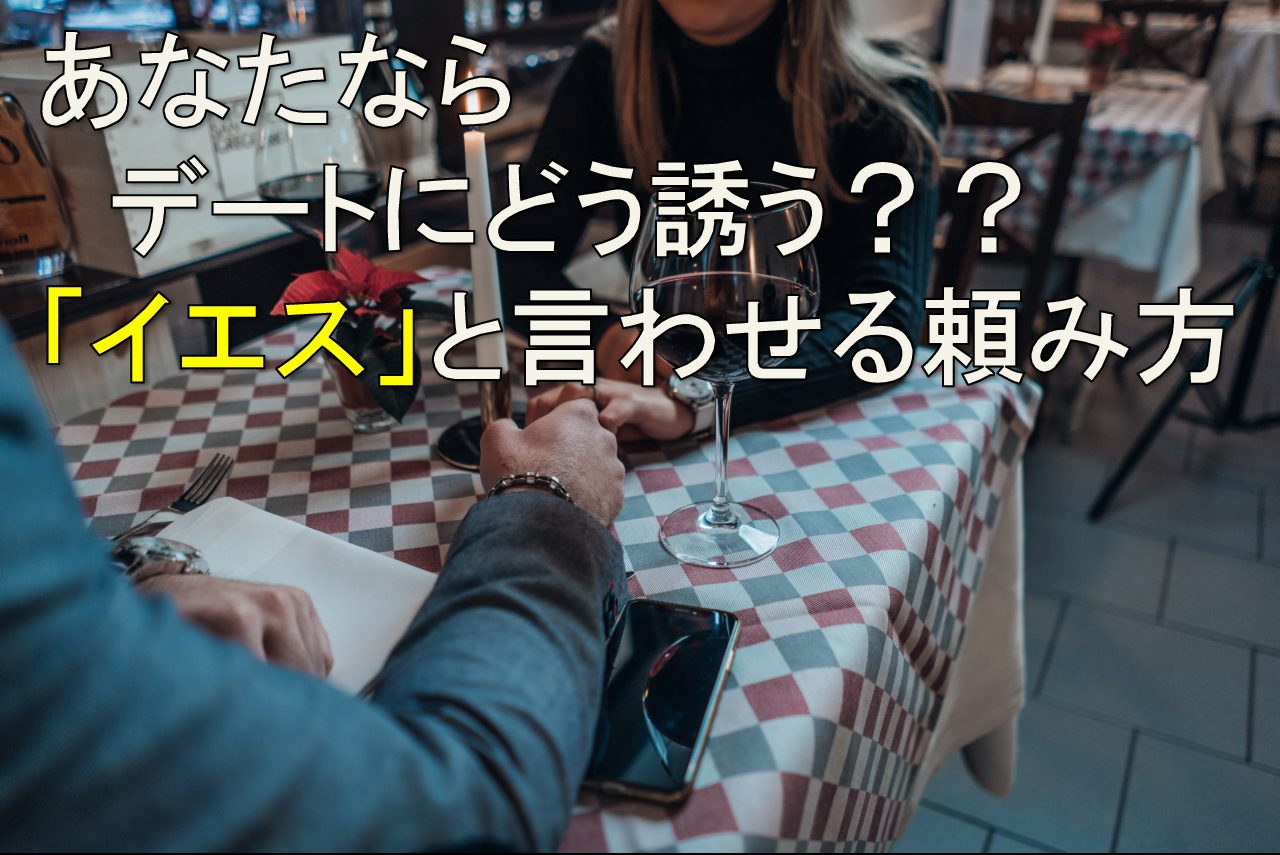こんにちは!技術者として仕事をしている現役理系サラリーマンのつぐっちゃんです。
ここでは仕事の進め方に悩むサラリーマンや会社でどう働くのか学びたい学生の方に向けて役立つコンテンツを配信しています!
今回は間違った判断に繋がる恐れのある思考のクセについて学んでいきましょう!!
<これだけはお伝えしたい!アクションプラン>
・前提が誤っていないか疑いの目を持つ
・与えられた前提はできるだけ具体化するように意識する
・物事に対して過去の経験や知識で安易に決めつけて判断しない
この記事の目次
思い込みや情報の信頼性を疑う
こちらの記事では、より良いアウトプットを出すための思考法としてクリティカルシンキングの必要性について説明しました。もしまだ読まれていない方はぜひ一度目を通してみてください。
本記事では、課題を認識する上で注意すべき思考のクセと気をつけるべきポイントを本書より3つピックアップしてご紹介します。皆さんもきっと共感するような事例もありますのでぜひ最後までお付き合いください。
間違った判断をしないためのアクション
前提が誤っていないか疑う
前提やデータを見るときは妥当性があるか考えてみる。
自分で論理的だと思っていても、気づかないうちに歪曲した前提をベースに理論を組み立てている事がある。
「ねぇ、お母さん、あのおもちゃ買って〜。タカシ君だって、マモル君だって持っているんだよ」
誰もが聞いたことのありそうなこの理屈は、自分にとって都合の良い前提に基づいた理論の典型的な例として挙げられています。この理論の問題点は3つ。
①サンプル数が明らかに少ないのに一般化している
「タカシ君とマモル君の2人が持っている」=「みんな持っている」という理屈だが、統計的に2つのデータだけでは信憑性は低い。
②サンプリングが偏っている
都合の良い前提とするために、あえておもちゃを持っている子だけを抽出している。
③そもそも前提が誤っている
あたかも「みんなと一緒でいないことは異常である」ともいうような前提で話している。
保険のおばちゃんの常套句「万が一に備えなきゃ、社会人になったらみんな入っているよ」や、化粧品のキャッチコピー「有効成分3倍配合!」など、特に勧誘や広告において、一見もっともらしく魅力的に聞こえる文言がありますが、よくよく考えると前提がおかしな事は多くありますよね。
そもそも納得のいく必要性や根拠があるのかどうか、冷静に見極めていきましょう。
抽象的な前提はできるだけ具体化する
課題や目標を抽象的な正論のままにせず、できるだけ具体化する。
「利益を高めるために、販売数量を20%UPする」「今年は無駄遣いをせずにお金を100万円貯金しよう」などといった課題や目標をよく目にしませんか。「利益を高める」や「無駄遣いをしない」といった前提は、言わば当たり前な正論で、往々として抽象的なレベルで思考停止していると述べられています。
「利益を高める」としたら、どの程度なら実現可能だろうか。市場の成長性や潜在顧客数、自社製品の評価、他社動向などから何割のシェアが取れる余地があるのか確認してみる。そうした具体的な数値を踏まえた上で課題設定する方が、上司も納得しやすく、かつより達成できる可能性が高まりそうですね。
前提を具体化する際のポイントとして、個人的に感銘を受けたものは「当たり前だとわかっていても、あえて書き出してみる(整理してみる)」ことです。
たとえ上司から「この商品はニーズがない」と言われても、その裏付け確認をとってみると実は根拠が薄かったり、昔の事実であったりする事がよくあると書かれていますが、実際にその通りだと思いました。情報や一般常識など、時間が経つと変わってきたり、実は根拠が間違っていたりすることはありますよね。偉い人や上司が言ったからといって鵜呑みにせず、都度自分なりに確認するように気をつけたいです。
トリガー効果(思い込み)に気を付ける
物事に対して過去の経験や知識で安易に決めつけて判断するのは避ける。
トリガー効果とはある一部の情報に触れた時に、大きなパターンを一気に認識することができる脳の機能となります。例えば、銀行にいる時にサングラスにマスク、帽子を着用した男が包丁を持っているのを見たら「強盗だ!」と瞬時に連想しますよね。
生き残るための危険予知としては非常に有用なこの機能ですが、仕事を取り進める上では誤った判断を引き起こす可能性があるため注意が必要です。なぜならば物事を判断する上で必須となる前提や事実を見落とす恐れがあるからです。
例えば10年前にテレビCMの広告を打ち出して、売上を大きく伸ばす経験をした人が今になってまた広告を出すことになった場合、果たしてどうするでしょうか。比較的最近出てきたSNSや動画サイトなど、より効率良く大勢にヒットする可能性のあるコンテンツを並べられても、恐らくまず同様にテレビCMを出そうとするでしょう。
つまり、一旦思考がなんらかのパターンに落ち着いてしまうと、似た場面において同じパターンだと認識する「思い込み」が生じてしまう。特に私たちが一旦過去からの信念や成功体験に縛られてしまうと、なかなかそこから抜け出せなくなってしまうため注意が必要です。
おわりに
いかがでしたか。このような思考のクセに注意して物事を捉えることで、誤った判断や困難な課題設定を避けていけるようになりたいですね。
また、このようなクセを悪用した商売は勧誘をはじめ身の回りの至る所に見受けられます。甘い言葉に安易に流されないようにお互い気をつけましょう。
本書には課題設定を実践するためのトピックスが他にも記載されています。もしご興味がありましたら、ぜひ手にとってみてください。
 | 入社1年目で知っておきたい クリティカルシンキングの教科書【電子書籍】[ 山中英嗣 ] 価格:1,400円 |