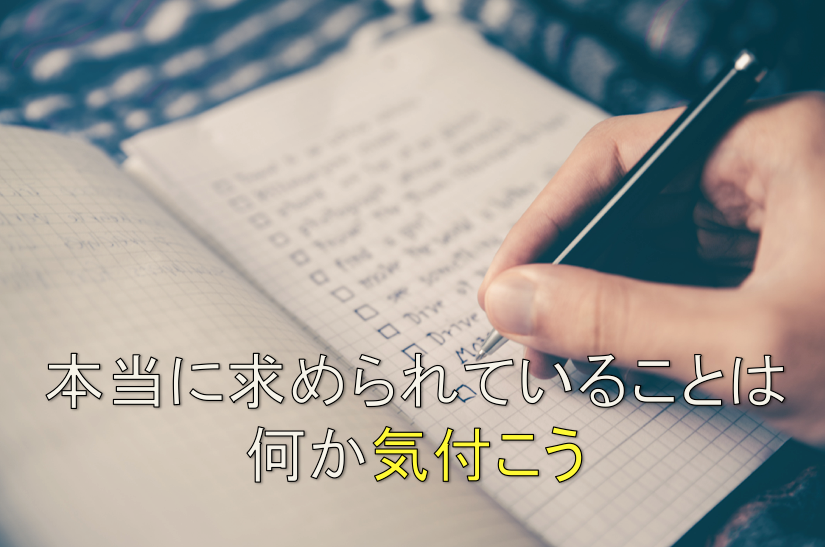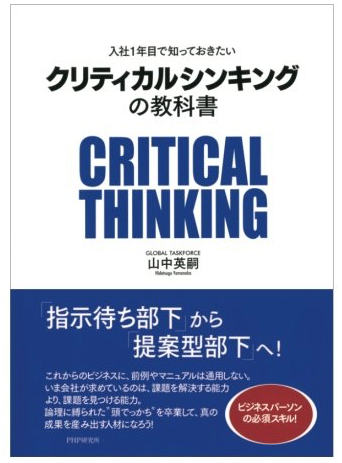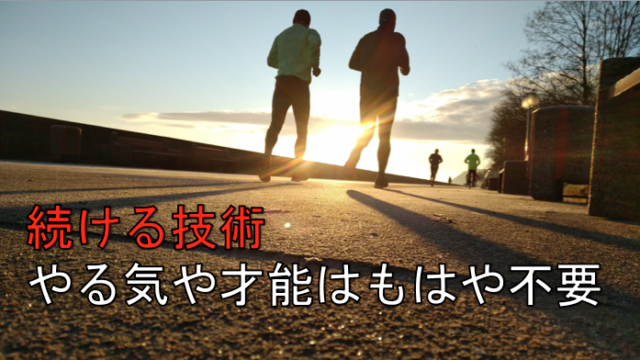こんにちは!技術者として仕事をしている現役理系サラリーマンのつぐっちゃんです。
ここでは仕事の進め方に悩むサラリーマンや会社でどう働くのか学びたい学生の方に向けて役立つコンテンツを配信しています!
今回は表には出てこない課題に対して気づきを得る方法について学んでいきましょう!!
<アクションプラン>
・目の前の仕事や作業を行う前に一旦立ち止まり、目的やプロセスについて考えてみる
・自分の意見を持つためのチェックリストを確認する
・幾つかの出来事について共通する原因やルールがないか考えてみる
気づきを身に付けるためのポイントまとめ
こちらの記事では、より良いアウトプットを出すための思考法としてクリティカルシンキングの必要性について説明しました。もしまだ読まれていない方はぜひ一度目を通してみてください。
本記事ではクリティカルシンキングを使いこなしたいと思った方に向けて、この思考法の構成要素の一つである「主体的な課題設定(気づき)」を身に付けるためのポイントを本書から3つピックアップしてご紹介します。
気づきの習得方法
自分の立ち位置を常に意識する
仕事に取り組む中で時折手を止めて、前提状況や課題の確認を行うことを習慣化する。
今自分のやっている仕事に無意識でありすぎると、課題に気づかなかったり、今の仕事の本来の目的を忘れることがある。そうならないように、目の前の仕事を行う前に一旦立ち止まって「ゴールは何か?制約条件は何か?このまま作業を進めて良いのか?」ということを考えることが重要だと主張しています。
つまり、このように自分の立ち位置を常に意識し続けることが、解決すべき真の課題を認識させてくれる(気づく)手助けになるということになります。
また仮に単純作業であっても、こうした姿勢で作業に臨むことでモチベーションを保つことができると述べています。例えば次の有名な<3人のレンガ職人>の話では、レンガを積むという単純作業に対する捉え方がそれぞれ違います。
<3人のレンガ職人への「何をしているか」の問いかけに対する答え>※引用先
●1人目:「レンガ積みに決まってるだろ」
●2人目:「この仕事のおかげで俺は家族を養っていける」
●3人目:「歴史に残る大聖堂を作っている」
この中で最もモチベーションが高いのは当然3人目の職人ですね。そしてレンガを積むという作業の目的を「レンガを積むこと」→「大聖堂を作ること」と再認識することで、作業の効率化といった課題だけでなく、大聖堂の完成度に関する問題に対しても気づくことができそうだと思いませんか。
チェックリストを活用する
例えピントがずれていても「自分の価値判断基準を持つ」という習慣をつけるため、チェックリストを作成して活用する。
「気づき」のサイクルを短く、速く、多く回していくことができるようになる(感度を鋭くする)ため、あらゆる物事に対して「自分のフィルターを通して整理、評価、判断する」ことを習慣化することが有効となると述べられています。
このように「自分の価値判断基準を持つ」習慣を身につけるための手段として、チェックリストを利用することが挙げられています。上司に仕事を依頼された時のチェック項目の例は次のように記載されています。
<チェック項目>※本書抜粋
①検証すべき仮説は何か?
②今自分が遂行している作業の最終目的は何か?
③成し遂げるべき行動レベルはどの程度か?
④そこに隠れている価値(例外や落とし穴)は何か?
⑤どのようなアクションで、いつまでに実行すべきか?
案件にもよると思いますが少々細か過ぎる気がしますね。正直重たいので、個人的には軽い依頼程度だったら、最低限⑤具体的なアクションと納期確認、②目的、③作業の完成度を確認できればいいかなと思いました。
また依頼されることのない通常業務についても、判断基準を通すことを意識しながら取り組んでいくことで、気づきを得るための感度を高めていきたいですね。
体系化して偏りをなくす
幾つかの出来事に対して共通する原因やルールがないか関連づけをして考える。
例えば「明らかな凡ミス」をして会社に大損害を与えた時の対策として、凡ミスをした人の個々の不注意に注目するのでなく、ミスが無くなるような、ダブルチェック体制やチェックリストを活用した作業に変更するといった、「統制の仕組みが会社になかった」ことに注目して立案すべきと述べられています。
仮にその人の不注意が原因として対策を打ってもそのミスが無くなることは考えにくいですよね。そもそも人間はミスを犯すものだという関連づけをすることで、ミスの検知や作業方法見直しへ繋ぐことができるということですね。
単に対症療法で終わるのではなく、真の原因について考える。特にトラブルやクレーム対応で再発防止を立案するときに重要となる考え方だと思いますので、ぜひ意識しておきたいですね。
おわりに
気づきを得るためのポイントについていかがでしょうか。本書には他に気をつけるべきポイントや多くの事例が記載されています。ご興味のある方はぜひ一読して見てください。
 | 入社1年目で知っておきたい クリティカルシンキングの教科書【電子書籍】[ 山中英嗣 ] 価格:1,400円 |