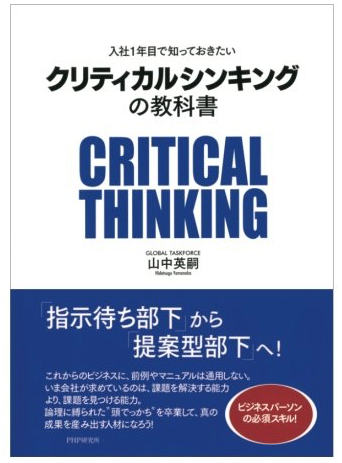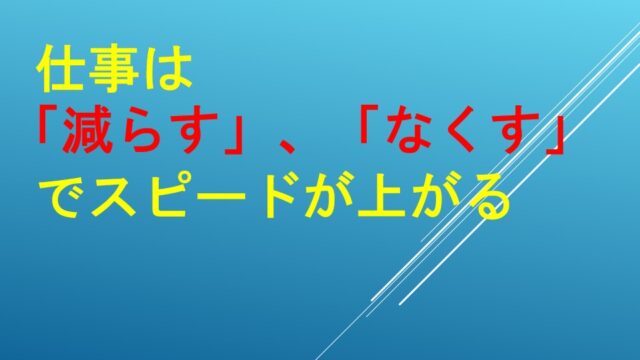こんにちは!技術者として仕事をしている現役理系サラリーマンのつぐっちゃんです。
ここでは仕事の進め方に悩むサラリーマンや会社でどう働くのか学びたい学生の方に向けて役立つコンテンツを配信しています!
今回は批判的思考クリティカルシンキングについて学んでいきましょう!!
<これだけはお伝えしたい!アクションプラン>
・課題についてまずは目的やプロセスについて自分なりに考えてみる。
・場面によって隠れた前提や本当の目的が何なのか考える。
・特にトレードオフな問題に対しては自分なりの判断基準を持って臨む。
この記事の目次
課題に対してより多面的に捉えるための考え方を身に付けよう
今直面している課題に対して、これまでの経験や知識からなんとなくで問題解決としていませんか。果たしてそれは最適な解決策と言えるのでしょうか。
与えられた仕事を実施する中で、いまいち手応えが無いなあと感じたり、やり直しが多い方はぜひ一度この「クリティカルシンキング(批判的思考)」の考え方を検討してみて下さい。
クリティカルシンキングとは
クリティカルシンキング=「主体的な課題設定(気づき)」+「ロジカルシンキング(論理思考)」
クリティカルシンキングとは、本書ではその場面における「判断基準」に基づいた思考を実践することと記載があります。個人的には「課題や業務について多面的に考え、その自らの考えを基により良い判断や行動(効果的なアクション)に結びつけるための考え方」と解釈しました。
本記事では具体的にどういった場面でこの考え方が役立つのか記載していきます。
クリティカルシンキングを活用すべき場面
詳しい「前提条件」や「命題」が提示されない依頼を受ける場合
与えられた前提だけで必ずしも満足のいく結果を得られるわけではない。場面によって隠れた前提や本当の目的が何なのか考え、自ら課題を再認識することで成果に結びつく判断や行動をとることができる。
例えば上司から「取引先と会食するのでレストランを予約しておいてくれ」と指示されたとき、なんとなく一般的に良さげなお店を食べログで検索してしまう。普段ありそうな事例ですが、本書ではこの場面における理想は「一般的に良い店を予約すること」ではなく「相手にとって良い店を予約すること」と述べています。
この事例では一見して上司の指示には従っていますが。上司の本当の目的は「レストランを予約すること」ではないのは想像できますね。また、「取引先の相手に満足してもらうこと」を目的とすると、次のように事前に把握しておくべきことが考えられます。
<事前に把握しておくべきこと>※本文抜粋
●相手は誰か?立場は?
●接待なのか、単純な打ち合わせなのか?
●相手の好き嫌いは何か?
●相手にとって便利なお店はどのエリアか? 等々
このように依頼に対して文字通りに無意識で行動する前に、自ら「主体的に前提を把握し、その前提から考えられる問題そのものを再定義し、仮説を設定したうえで、解決に向けた行動をとる」ということを意識的に実践することで成果に結びつくと主張しています。
この場合は問題を「相手にとって良い店を予約すること」と再定義していますが、そもそも詳細な前提情報や本当の目的は与えられることが少なく、これらは「自ら意識的に」必要としない限り見えてこないので注意が必要ですね。
「これよろしく」と頼んでくる場合
目的や背景が曖昧なまま依頼を受けるのは危険。仮に迷惑がられても聞いておくことでより良いアウトプットに結びつく可能性が高まる。
またこの事例から、「これよろしく」や「会議の資料作っておいて」などと仕事を任されることが連想されました。少なからず遭遇する曖昧な脈絡で来るこれらの依頼は前提条件や命題が不足している典型的な例といえますね。
このような依頼に対しても同様に自ら前提を把握して、何を求められているか考えるべきです。逆にいえば、相手の意図が分からないまま表面上仕事をこなしていても、アウトプットに満足してもらえることは少ないと思います。せっかく時間をかけてやるのであれば相手に納得してもらいたいですよね。
求められていることは何なのか、特にこういうときは可能ならその場で必要な情報を聞いた方が良いと考えます。よく忙しそうだからと変に空気を読もうとしたり、仕事ができない奴と思われるのが嫌だと見栄を張ったりして二言返事で安易に受けてしまいがちですが、後からだと当の本人がなかなか捕まらないことはよくありますね。
「リスク」と「リターン」がトレードオフな問題について判断する場合
本当に解決が難しく、悩ましい問題は、常に「リスク」と「リターン」の間のトレードオフの判断の問題である。このような問題はその判断材料と具体的な選択肢を主体的に持ち合わせ取り進めなければ解決することはない。
こちらは事例として、「自社の利益を上げる」という課題について述べています。ビジネスをする上で必ず直面する課題ですが、利益を上げるための必要な選択肢を次のように列挙しています。もし過去の販売実績やマーケット状況などから候補を挙げるだけであれば、それほど難しくないかもしれないです。
<利益を上げるための選択肢>※本文抜粋
「売上を上げるかコストを下げる」
●売上拡大のためターゲット顧客リストを整理する
「A社を攻めるか、B社を攻めるか」
●同様に販売促進を強化するべき製品を整理する
「C製品を強化するか、B製品を強化するか」
しかし、これらの選択肢から自社にとっての最善策や次善策を判断しようとするとなかなか決めきれません。なぜなら、それぞれの選択肢一つ一つに自社にとってのメリットだけでなくデメリットやリスクといった複雑なトレードオフがあり、それを全体として把握したうえで最終判断する必要があるからです。
自社の方針に基づいて利益を最大化させるため「どういった選択肢の組み合わせがベストか?それはなぜか?」考える場合、何を得ることを優先して、どこまでリスクを取れるかはその時点の状況によって変わってきますよね。そんな時はその場面における「判断基準」を自ら考え、その基準に基づいて判断することでより良い成果に結びつくと述べています。
まずは課題について主体的に考えてみることから
クリティカルシンキングの考え方について、その必要性は感じていただけたでしょうか。私は本書を読んで考え方云々より、課題についてやらされていると思わず、まずは目的やプロセスについて自分なりに考えてみることがより良いアウトプットには必要なのだと考えました。皆さんはいかがでしょうか。
「とは言っても結局具体的に何をしたらいいの?」と思われる方もいらっしゃるかもしれません。安心してください。本書には、気づきを身につけるためのヒントや物事をより多角的に見るための工夫、課題認識をする上での注意事項などクリティカルシンカーになるための手法についても記載されています。
興味のある方は本書を購入していただくか、個人的にも為になるトピックスだと思いますので、順次記事にしていこうと考えています。


 | 入社1年目で知っておきたい クリティカルシンキングの教科書【電子書籍】[ 山中英嗣 ] 価格:1,400円 |